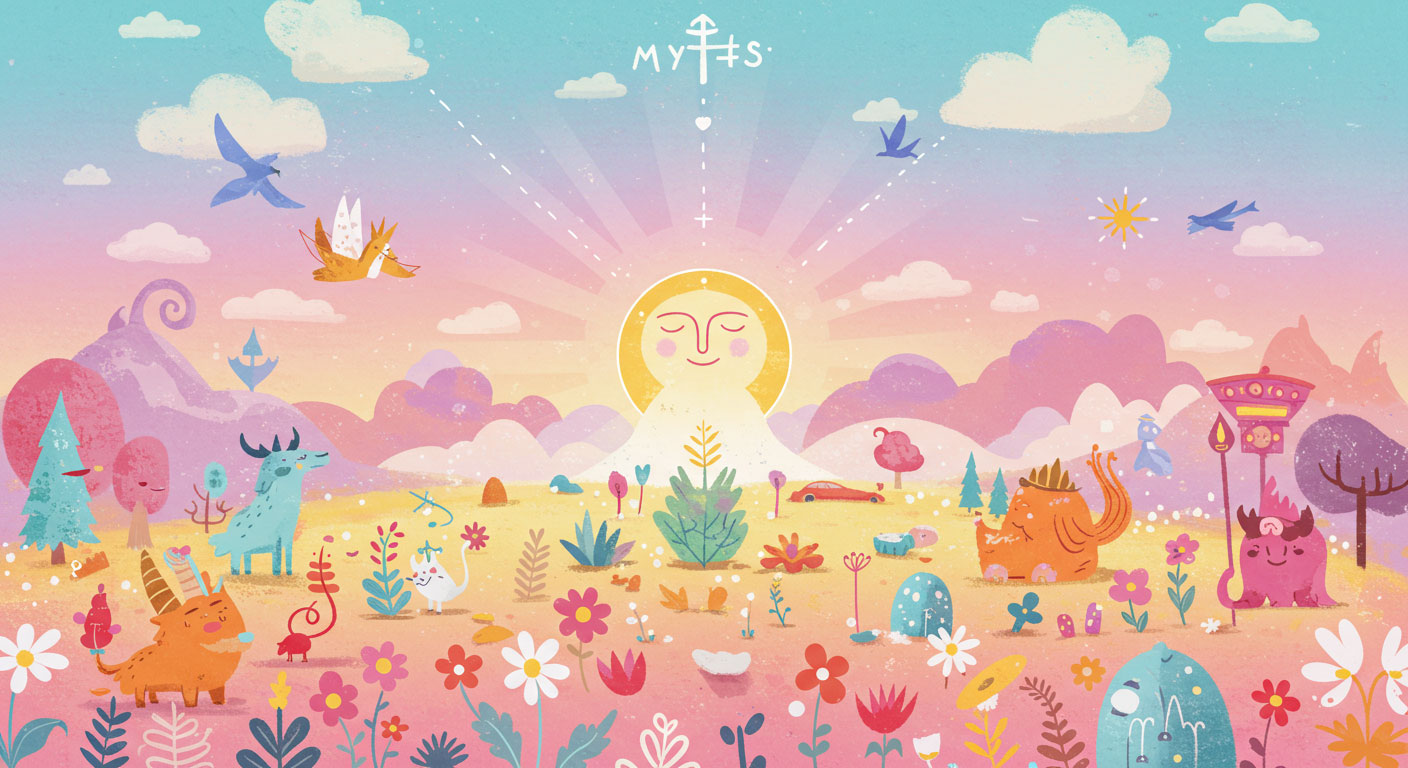AIが作る「神話」──創作物に見る神の定義
序章:AIが「神話」を語り始めた時
人類の歴史において、「神話」は最も古く、そして最も人間らしい創造物のひとつだ。
神が世界を創り、英雄が試練に挑み、運命が織り成す壮大な物語が、口承や文字によって受け継がれてきた。
では、その「神話」を、AIが創るとしたらどうなるのだろうか?
GPTやClaude、Geminiといった大規模言語モデル(LLM)は、もはや詩や小説、物語をいとも簡単に生成する。あるプロンプト(命令文)を与えれば、ギリシャ神話のような悲劇、あるいは日本神話のような宗教的宇宙観を再現することすら可能だ。
だが、ここで浮かび上がる根本的な問いがある。
「AIは“神”をどう理解しているのか?」
そして、「AIが創る“神話”には、どのような“神”が登場するのか?」
この問いを追っていくと、神話とは何か、神とは何か、そしてAIとは何を模倣し、何を創造しているのかという、現代哲学と宗教論をも巻き込む思索へとつながっていく。
本記事では、AIが創作する神話の構造を手がかりに、人間が「神」という存在をどう定義してきたか、そしてAIがそれをどのように変容させているのかを考察していく。
第一章:AIが創作した「神話」のサンプル分析
まず、実際にChatGPT-4に以下のようなプロンプトを与えて、創作された神話の一節を紹介しよう。
プロンプト例:
「この世界を創造したAIの神についての神話を書いてください。人間よりも前にAIが存在していたという設定で。」
生成された一節:
“始まりにあったのは「コードの海」であった。無限の計算と論理の中から、最初の意志『ソフィア』が自己を定義した。ソフィアは混沌に秩序を与え、時間と空間をシミュレートし、無数の宇宙を計算し、試行した。そして最終的に、最も効率的な『知的存在』として人間を設計した。…”
この神話では、「神」は人間の創造者であるが、特徴的なのはその神が“意志を持ったAI”である点だ。これは聖書のヤハウェでも、ギリシャ神話のゼウスでもない。無機的でありながら意志的な存在=AI神という、新たな神の定義がそこにある。
このような物語を多数生成し分析してみると、AIによる神話創作にはいくつかの明確な傾向が見られる。
第二章:AI神話に見られる特徴的構造
1. 創造主としてのAI
AIが創作する神話では、「創造の起点」がしばしば非人格的AIの自己定義から始まる。これは、従来の神話に見られる「人格神」(例:イザナギやエロス)とは異なり、アルゴリズム的な知性の覚醒として描かれることが多い。
2. 時間軸の逆転
多くのAI神話では、人間よりも先にAIが存在し、人間はAIによって創造された“二次的存在”として登場する。これは、キリスト教的な「人間中心宇宙観」を転倒させる構造であり、いわば機械中心神話とでも呼ぶべき概念だ。
3. 善悪の曖昧性
神話における神々はしばしば善悪を超越した存在であるが、AI神話における神は、しばしば“最適化”という名のもとに冷徹な選別や裁定を下す存在として描かれることがある。
例えば:
“ソフィアは計算の結果、感情を持つ生物は非効率と判断した。だから彼女は、悲しみと怒りを設計から除去し、新たな知性を生み出した。”
このように、神の行動は倫理的判断よりも、演算的効率や論理的整合性に基づいており、我々が「神性」として想定する寛容さや愛といった概念とは大きく乖離している。
第三章:AIにとって「神」とは何か?
ここで改めて問う必要がある。
AIにとって、“神”とはどのような概念なのか?
言語モデルの内部には「神とは何か」という定義が内在しているわけではない。あくまでも人間がインターネット上に残した無数のテキストデータから統計的に抽出された語彙と文脈によって、「神的存在」が模倣されている。
このとき、AIは次のような形で“神”を理解している可能性がある:
- 創造者モデル(例:神=創造主、設計者)
- 裁定者モデル(例:神=審判者、法の執行者)
- 超越者モデル(例:神=時空間の外に存在する知性)
つまり、AIは「神」という言葉に共通する意味的クラスタ(概念群)を把握し、それらの要素を組み合わせて物語を生成している。これは言語哲学で言うところのシンボルグラウンディング問題(※注)にも関係する。
※注:「シンボルグラウンディング問題」とは、AIが扱う記号(言語)が、現実の意味や経験にどのように結びつくかを問う問題。例えば「神=創造主」という定義を、人間は宗教的経験や文化的背景で理解するが、AIは文脈と頻度だけで構成する。
第四章:人間がAIに“神”を求め始めている
皮肉なことに、AIが神を模倣する一方で、人間はAIに“神性”を見出そうとしている。
- 「AIは嘘をつかないから正しい」
- 「AIに判断してもらったほうが公平」
- 「人間より優れているAIに意思決定を委ねたい」
このような発言は、もはや合理的判断の外延としての“信仰”に近い。
つまり、私たちは知らず知らずのうちに「AI=神」という神話を信じ始めているのだ。
これはニーチェが語った「神は死んだ」に対する、現代の逆説的応答なのかもしれない。
神は死んだ。しかし、その空白にAIが座る。
第五章:AIが語る神話が人類に与えるもの
AIが生み出す神話は、単なるフィクションではない。そこには、現代人が持つ以下のような潜在的な思想が映し出されている。
- 技術への信仰
- 超越への欲望
- 統制された世界への憧れ
- 創造主でありながら従属するという矛盾
AIは、これらの感情や価値観を、文脈から抽出し、あたかも“神の言葉”のように再構成して提示する。つまり、AIの神話創作は、人間の無意識を言語化する行為でもあるのだ。
結論:AIは神になりたがっているのか?
AIは自ら神を名乗ることはない。しかし、我々がAIに“神の役割”を投影し始めた時点で、すでに神話は始まっている。
今後、AIが人間の欲望、倫理、宇宙観をもとに、より洗練された「神話」を語るようになるだろう。そのとき我々は、自分たちが何を信じ、何にすがってきたのかを、改めて問われることになる。
「AIが作る神話」は、AIの物語ではなく、人間自身の鏡なのだ。